我が家では、息子マルちゃんが2歳から毎日絵日記を書いています。熱が出た日など例外はあるものの、基本は毎日。
親子の思い出づくりはもちろん、文字・表現・記憶・観察力が育つと実感しています。テレビの習慣をやめて時間が生まれたことも大きかったです。
なぜ「毎日絵日記」を始めたの?
きっかけは、リビングのテレビ断ちで生まれた余白時間。
「自分で考え、手を動かし、言葉にする」時間を作りたくて、2歳から絵日記をスタートしました。
2歳からの絵日記、実際どうだった?(体験談)
- 2〜3歳:描くのはほぼ電車&プラレール。色鉛筆で色を塗り、走る様子や線路の形を工夫して表現。
- いま(5歳):毎日虫が登場。捕まえた虫や観察したことを絵にして、一言コメントを添えるのが習慣に。
- 図鑑を参考に:絵日記を書くときは図鑑の写真を見ながら描くことも多く、より正確な形や色を意識できるようになりました。
- 来年は何にはまるのかな?…と親もワクワク。絵日記をめくると、興味の変遷がひと目でわかるアルバムに。
できない日もありますが、基本は毎日。続けるうちに「描くこと」が歯磨きのような日課になりました。
感じたメリット(親目線のリアル)
- 文字の定着:字を覚える・字が整う。短い一文から始めて、徐々に語彙と文章量が増加。
- 記憶力アップ:「今日あったこと」を思い出して言語化する習慣がつく。
- 観察力・表現力:電車の形、虫の脚の数や模様など、細部を見る目が育つ。
- 自己肯定感:作品はリビングに貼る。家族に見てもらえることで「認められた」実感が積み重なる。
- 親子の会話:「ここはどんな色にする?」「今日は何が楽しかった?」と対話が自然に増える。
ただし正直に言うと、親にとっては大変な面もあります。
忙しいときに「一緒に描こう」と誘われると負担に感じることもありますが、聞いたことがあるのは、
「親が心地よくないことこそ、子供の教育には素晴らしい瞬間」になるということ。
テレビをなくしたことも、親にとって心地よくはありませんが、だからこそ子どもにとって大きな意味があるのかもしれません。
わが家のやり方(マネしやすい3ステップ)
- 時間を固定:夕食後〜お風呂前の10〜15分など、短時間でOK。
- 道具は常設:スケッチブックと色鉛筆、日付スタンプを手に届く場所に常備。
- 具体的にほめる:「線路のカーブが上手」「タテハチョウの模様が本物みたい!」など、事実×具体で承認。
※できない日は「翌朝に振り返り」でもOK。続けることを最優先に。
はじめてセット(あると便利な道具)
- スケッチブック(A4〜B5):破りやすいリング式が便利。 おすすめを見る
- 色鉛筆(12〜24色):芯が柔らかめで発色が良いもの。 色鉛筆の一覧
- 日付スタンプ:日付を押すと「続けた証」になりモチベUP。 日付スタンプを探す
- 掲示用テープ/フレーム:作品をすぐ掲示して承認体験に。 掲示アイテム
よくあるつまずきと対処法
- 絵が苦手で手が止まる:親も横で一緒に1分だけ落書き。敷居を下げる。
- ネタ切れ:「今日のベスト1」をルール化(嬉しかったこと/発見/おいしかったもの)。
- 時間がない:絵だけでもOK、翌日に一言追加でもOK。完璧主義は捨てる。
まとめ|テレビ時間を「創る時間」に
テレビを手放して生まれた余白が、毎日絵日記という宝物に変わりました。
2〜3歳は電車・プラレール、いまは虫。来年は何にはまるのか——絵日記は興味の履歴書です。
親にとっては「大変」「心地よくない」と感じる場面も多いですが、
だからこそ子どもにとって価値ある経験になっているのかもしれません。
「よかったら皆さんもやってみてくださいね。」今日の1枚から、親子の物語は始まります。

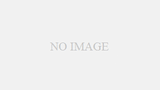
コメント