ロボットが合体し、“爆弾”(ごっこ)を火で温めて起動、火星へ“悪者役”を飛ばす――。テレビをほとんど見ないマルちゃん(祖父母宅でアンパンマンやトーマスを少しだけ)の発想は、もともとの天体好きと、名古屋のトヨタ産業技術記念館で見た「熱で鉄を溶かす」実演体験が結びつき、体験×興味の掛け算で一気に“宇宙規模”へ広がっているようです。
エピソード:電車からロボットへ、そして父子ミッション
少し前までは、ニューブロックの主役は“電車”。レールを作って走らせるのが定番でした。それがいつの間にか、今はロボットに夢中。マルパパを誘ってロボット対決をする日もあれば、協力して「太陽を壊そう(=太陽エネルギーのコアを停止させるごっこ)」という壮大なミッションになることも。
ただ今のところ、マルちゃんは“負け”をまだ受け入れられないみたい。マルパパが「たまには勝たせてよ」と言うと、「明日ね」と応じるけれど――マルパパの勝利シーンは、まだ我が家では観測されていません(笑)。
1. ニューブロック×宇宙ごっこ=発想の伸び代しかない
- 合体:パーツを組み替え、役割と強度を最適化=モジュール設計の感覚
- “温める”:エネルギー投入→状態変化(鉄→溶融、爆弾→起動という物語的変換)
- 火星へ飛ばす:推進・軌道・目的地というミッション思考
ブロックは造形だけでなく、物理・工学・物語を一体化させる最高の舞台です。
2. アイデアは「見た・感じた・覚えている」から生まれる
- 天体図鑑や星の会話 → 宇宙への方向性
- 産業技術記念館の溶解デモ → 熱と変化のイメージ
- アンパンマン/トーマス → 善悪・役割・チーム(合体)の抽象モデル
これらが頭の中でブレンドされ、ニューブロック上に“火星ミッション”として再構成。つまり、体験の転用(トランスファー)が確かに起きています。
3. 遊びの中のSTEM要素をそっと言語化
親のひとことが、学びを静かに底上げ。
- 構造:「この合体、どこが一番強い?」(強度・支点)
- エネルギー:「温めたら何が変わる?」(状態変化)
- 推進:「火星までどうやって行く?」(距離・時間・燃料の概念ごっこ)
- 設計:「今日のミッション名は?」(目的→工程→評価)
4. 伸びている力(非認知+認知)
- 創造力・物語化:設定→合体→起動→到達の因果の糸を紡ぐ
- 観察→再構成:見た体験を遊びに置き換えるトランスファー
- 語彙と論理:「爆弾」「温める」「火星」を意味ネットワークで接続
- 自己決定感:テレビに依存せず、自分の世界を起動できる
5. 父子バトルと“負けの練習”を、楽しく育てる
- 勝ち筋を作る対戦:わざと拮抗させて「最後の一手」で逆転される体験を演出
- 引き分けの設計:制限時間や“同時着陸”ルールを導入
- 負けのリフレクション:「次はどこを強くする?」と改善の視点に橋渡し
※「太陽を壊す」はごっこの中で。本当の火は大人と一緒のルールを毎回セットで。
6. 家でできる“宇宙ミッション”発展アイディア
- ミッションログ:A6ノートに「ミッション名/合体図/結果」を1分メモ(絵でOK)
- 素材ラボ:アルミ箔・紙コップ・キャップで“耐熱シールド”“燃料タンク”を自作
- 着陸ゲーム:床にテープで“火星基地”。10→0で着陸成功!
- ストローロケット:紙+ストローで簡易ロケット(推進を体感/安全に)
- 温度と変化ごっこ:氷→水→湯の変化を観察(やけど注意)
まとめ:体験が、空想に翼をつける
ニューブロックのロボット合体から“温める”イメージ、そして火星へ。マルちゃんの“宇宙”は、図鑑・ミュージアム・身近な会話という現実の断片から組み上がる、立派な探究の入口。このまま観察→設計→実験→記録の小さなサイクルを、楽しみながら回していこう。

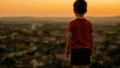
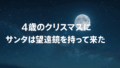
コメント