モンテッソーリ教育的に言えば、今のマルちゃんはまさに「書く敏感期」。毎日のお手紙、絵日記での漢字ブーム、そしてカタカナの使い分け——書くことが心と知性の成長に直結しています。
モンテッソーリ教育的に言えば「書く敏感期」
モンテッソーリ教育では、子どもが特定の行動に強く惹かれる時期を敏感期と呼びます。なかでも「書く敏感期」は4〜6歳頃に訪れやすく、子ども自身の「書きたい」「伝えたい」という内発的動機がスイッチとなって文字表現に熱中します。
マルちゃんにもこの時期がやってきました。私が少し疲れてため息をつくと、
「ちょっと待って!」と机に走り、お手紙を書いて持ってきてくれます。
「おかあさん、だいじょうぶ? ちょうしはどう?」
マルちゃんからのお手紙
まだ字は不揃いでも、そこには思いやりと言語表現の芽がしっかり育っています。まさに「手は脳の道具」というモンテッソーリの言葉どおり、書く行為が心と頭を結びつけています。
「書く」を通して広がる知的好奇心(漢字・カタカナ)
最近は漢字ブーム。毎日のルーティンで取り組む絵日記でも「これ漢字で書きたい!」と自分から提案します。「木」「川」「虫」など身近な言葉を漢字で書けると、マルパパ虫博士が「すごい!」と全力で称賛。称賛→自己効力感→次の挑戦という好循環が生まれ、学びの意欲が加速しています。
さらにカタカナにも自然な関心が芽生えました。以前、「カタカナは外国から来た言葉に使うよ」と話したことを覚えていて、
- 「パンは外国から来たんだよね」
- 「プラレールも外国からだね」
と会話の中で使い分けようとします。少し難しい概念でも、自分の言葉で意味づけしながら世界を広げているのが伝わってきます。
モンテッソーリ的に見る「書く力」は心の成長
モンテッソーリでは「手は脳の道具」。書くことは運筆だけでなく、思考・感情・観察力・自己表現を同時に育てます。マルちゃんにとって文字は記号ではなく「相手に気持ちを届ける道具」。お手紙は非認知能力(思いやり・自己コントロール・やり抜く力)を養う時間でもあります。
私自身が感じた「親の迷い」と「きっかけづくり」
実は私も、マルちゃんがまだ字が書けなかったころ、何度もネット検索をしました。「何歳になったら字が読めるの?」「ひらがなが書けるようになるのはいつ?」「カタカナは?」——と。
いろいろ調べたうえで、最終的に私が決めた目標は、「小学校入学までに、ひらがな・カタカナ全部、1〜10までの数字、自分の名前を漢字で書けるように」というもの。いま、5歳のマルちゃんはすでにクリアし、次のステップとして小学校1年生で習う漢字を楽しみながら覚えているところです。
ここまでの道のりは「教え込み」ではなく、きっかけを与えて見守るというスタンスでした。我が家では毎日の絵日記が、そのきっかけになっています。継続の中で「新しい字を書きたい」という欲求が自然に高まり、「カタカナはお父さんより上手!」と褒められた経験がうれしくて、学びが加速しました。
子どもの学びは、親が押しつけるものではなく、“楽しさ”の積み重ねの中にある。ある教育本で読んだ「子どもは生まれたときは完璧な存在。環境によって良さが削がれることがある」という言葉を胸に、これからも才能を信じ、きっかけづくりに専念していきたいと考えています。
家庭でできる環境づくり(再現性のある実例)
- 道具を常設:鉛筆・色鉛筆・短いメモ・小さな封筒を子どもの手が届く場所に。
- 言葉がけを変える:「書きなさい」ではなく「書いていいよ」「届けたい人いる?」。
- アウトプットの場:お手紙は読む・喜ぶ・飾る。家族掲示板を作るのもおすすめ。
- 実体験から言葉へ:散歩や観察後に絵日記→漢字1文字を一緒に確認(例:「木」「川」「虫」)。
- カタカナは意味づけ:「外国から来た言葉だよ」など概念→用法の順で自然に。
まとめ|“書く敏感期”は心と言葉が結びつく黄金期
今のマルちゃんは、書くことを通じて「思いやり」と「言語表現」を同時に伸ばしています。親としては、静かに整えた環境でその意欲を支え、届いたお手紙を大切に受け取るだけで十分。今日もまた、机に向かう小さな背中を見守りたいと思います。
よくある質問(幼児の文字教育・モンテッソーリ)
Q. 「書く敏感期」はいつ始まりますか?
A. 個人差はありますが4〜6歳に現れることが多いです。合図は「自分から書き始める」「手紙やリストが好き」など。
Q. 漢字はいつから?教えてもいい?
A. 興味が先行したらOK。生活語(木・川・虫など)から始め、形の面白さを味わわせるのがおすすめです。
Q. カタカナはどう教える?
A. 「外国から来た言葉」という意味づけから入ると自然に使い分けられます。パン、バス、カメラなど体験語から。
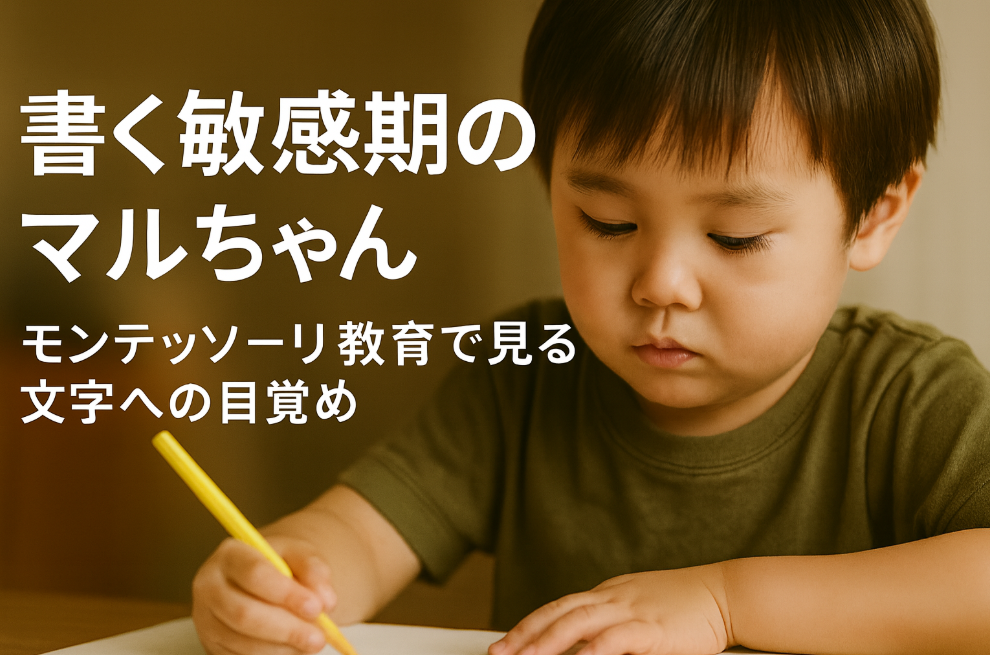
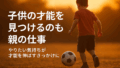

コメント