3子どもの「いってらっしゃい」は最高の教育|見送り習慣が育てる自己肯定感と家族の絆
朝の「いってらっしゃい」。
それは大人にとっては何気ない一瞬でも、子どもにとっては一日の始まりを安心して迎えるための大切な時間です。
3歳の少し前から、毎朝お父さんをお見送りするのが日課になったマルちゃん。
この記事では、その日常の中で感じた「見送り習慣の教育的効果」と「家族に生まれる幸せ」についてお伝えします。
泣いても欠かさない「お見送り」が育てるもの
ある朝、寝坊してお父さんの出発に間に合わなかった日がありました。
マルちゃんは目を覚ますなり「お見送りできなかった!」と大泣き。
まだ3歳になったばかりの頃でしたが、それほどこの習慣が心の拠りどころになっていたのだと思います。
この出来事をきっかけに、私は「習慣には心を安定させる力がある」と実感しました。
決まった時間に同じ行動を繰り返すことで、子どもは安心感を得ます。
「今日もいつもの朝が始まる」という感覚が、自己肯定感や生活リズムを整えていくのです。
雨の日も笑顔で「いってらっしゃい!」
雨の日もマルちゃんは小さな傘をさして、家の塀の外から身を乗り出して大きな声で言います。
「バイバーイ!また虫捕まえてね!」
その声は近所まで響きわたります。
通りがかった方々に「朝から元気だね」「声を聞くと元気になるよ」と声をかけていただくことも増えました。
小さな子どもの挨拶が、地域にも小さな明るさを届けている。
そんなふうに感じます。
このような日々のやり取りの中で、マルちゃんは「挨拶」「思いやり」「人との関わりの心地よさ」を自然に学んでいます。
社会性は教え込むものではなく、こうした毎日の関わりの積み重ねの中で少しずつ育っていくのだと感じます。
マル家のルール:「挨拶は元気よくだれにでも」
マル家には小さなルールがあります。
それは、**「挨拶は元気よくだれにでも」**ということ。
朝起きたらまず家族に「おはよう!」。
公園で虫取りをしているときも、すれ違う人には必ず「こんにちは!」。
時には、すれ違ってすぐに「いま僕、挨拶できたでしょ?」と得意げに話してくれることもあります。
少し声が大きすぎて「聞こえるよ〜!」なんて返すこともありますが(笑)、
その自信に満ちた表情を見ると、「人に元気に挨拶できることが、自信の芽になっているんだな」と感じます。
この“挨拶のルール”は、親が決めたものではなく、いつの間にかマルちゃん自身が楽しみながら続けている習慣です。
挨拶を通じて人とつながる体験が、彼の社会性と自己肯定感を確実に育てています。
パパにとっても、何よりのエネルギー源
マルパパは軽自動車で通勤しています。
時々高級車とすれ違っても、「自分の方が幸せだな」と言うのが口癖。
毎朝の見送りが、彼にとって一番のエネルギーチャージになっているのです。
「朝の『いってらっしゃい』と、帰宅後の『おかえりなさい』。
その二つで一日が報われる」と、マルパパはよく話します。
どんなに忙しくても、家を出るときに笑顔で手を振ってくれる存在がいる。
それは大人にとっても最高のモチベーションであり、家族の絆を強くしてくれる時間です。

「いつまで続くのかな?」と思う幸せな習慣
マルパパはときどき言います。
「何歳までお見送りしてくれるんだろうね」
きっと、小学校に入れば朝の支度で忙しくなり、中学・高校になれば恥ずかしさも出てくるでしょう。
それでも、この習慣がもたらしてくれた時間は、きっと一生の宝物です。
朝のたった数分の中に、愛情・成長・学びが詰まっています。
「お見送り」は、子どもの心を育てると同時に、親にとっても“今”を大切に感じさせてくれる尊い瞬間です。
まとめ|「いってらっしゃい」は小さな教育
子どもの見送り習慣は、単なる日課ではありません。
それは心を育てる家庭教育の一つであり、
・自己肯定感を高め
・社会性を育み
・家族の絆を深める
――そんな力があります。
忙しい朝でも、ほんの数分の「いってらっしゃい」で子どもは安心し、自信をつけ、親は幸せを感じます。
この当たり前の時間を、できるだけ長く、丁寧に味わっていきたいものですね。
そしてもし同じように「毎朝のお見送り」をしてくれるお子さんがいるご家庭があれば、ぜひその瞬間を写真や日記に残してみてください。
きっと将来、家族の宝物になります。

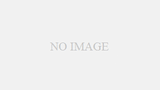
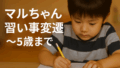
コメント