幼稚園で「遊ぼ?」と聞かないと遊べないマルちゃん。断られたら虫取りへ――虫はいつでも友達。5歳の彼の“安心と探究の時間”から、親としてできることを考える。
- はじめに:マルちゃんの今の姿
- 遊びの発達段階と「一人遊び」の意味
- なぜマルちゃんは“虫”が好きなのか
- 虫好きが持つ教育的・非認知能力とのつながり
- 親としてできること:支えるための工夫
- マルちゃんへのエール
- まとめ
はじめに:マルちゃんの今の姿
マルちゃんは年中(5歳)の男の子。幼稚園で遊ぶとき、遊びに入る前に必ずこう聞きます。
「〇〇くん、遊ぼ?」
その一言がないと安心できず遊びに入れません。要領よく、何も聞かず自然に遊び始める子もいます。そんな中で、マルちゃんは「遊ぼ?」を自分なりのルールにしています。だから時には友達に断られることも。
「今はダメ」と言われると、彼は諦めてひとりで虫取りを始めます。マルちゃんにとって、虫はいつでも遊んでくれる“友達”。
虫の話になると、言葉はとても達者。お友達の理解が追いつかないほど先に話してしまい、結果的にひとりになることも。親として「自然に混じっていいよ」と伝えていますが、マルちゃんなりの“流儀”があります。
遊びの発達段階と「一人遊び」の意味
発達心理学のモデル(パーテンの遊びの分類)では、ひとり遊び→傍観遊び→平行遊び→連合遊び→協同遊びと進むとされます。5歳前後は連合〜協同遊びへ移る時期。
「遊ぼ?」と聞かないと入れないのは、自然に輪へ入るステップを練習中というだけで、発達の流れの中にあります。
なぜマルちゃんは“虫”が好きなのか:虫との時間の意味
- 安心感のある相手:友達に断られるかもしれない緊張がない。虫は拒否しない、だから心が落ち着く。
- 自由な探究心:どこにいる?どう動く?図鑑で調べる?――自分のペースで興味を追える。
- 五感と観察力:色・動き・匂い・土の質感。自然に触れ、集中力・想像力・思考力が育つ。
こうした虫との時間は、マルちゃんにとって“居場所”であり、安心して自分を表現できる大切な時間でもあります。だから今のマルちゃんは虫が大好き。この物語は、当サイトの他記事(例:オニヤンマ観察・捕まえ方ガイド/ヤゴ飼育と羽化の記録 など)ともつながっています。
虫好きが持つ教育的・非認知能力とのつながり
- 観察・探究:生態や環境への感受性が深まる。
- 非認知能力:集中力・自己肯定感・粘り強さが育つ。
- コミュニケーションのきっかけ:虫好き同士で話が弾み、図鑑や発見の共有が交流の入口に。
親としてできること:支えるための工夫
| 方法 | 具体例 |
|---|---|
| 声かけのバリエーション | 「いま何してるの?」「これ一緒にやってみる?」などの声をかけ、断られても「じゃああとでね」と返す練習をする。 |
| 観察・探究の場 | 虫図鑑を使う・虫かごで観察・公園や庭で虫探しを定期的にする・発見を話したり写真を撮る。 |
| ロールプレイやシミュレーション | 家で遊びの誘い・断り・他の選択肢などを一緒に練習しておく。 |
| 園・先生との連携 | 幼稚園の先生に「入りやすい声かけ」をお願いする。「いっしょにやろう」「入っていいよ」と言ってもらえるように。 |
| 好きの承認 | 虫を見つけたり触ったりしたこと、発見したこと、小さな挑戦をしたことを具体的に褒める。 |
マルちゃんへのエール
「遊ぼ?」と勇気を出して声をかけられること。断られても自分の好きで心を満たせること。そのどちらも、君の強さ。無理に変える必要はない。少しずつ“自然に入る”力も育っていくから。
まとめ
- 「遊ぼ?」は、いまの彼にとって安心のための手順であり、まだ成長の途中。
- 虫との時間は、観察力・集中力・情緒の安定に繋がる。
- 親は、好きなことを認めつつ、遊びの“入口”を少しずつ増やす支援を。
- 虫好きはマルちゃんの個性であり強み。将来の可能性を支える土台になる。

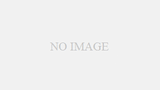
コメント