知育や教育の記事でよく出てくるキーワード「自己肯定感」。
「子どもの自己肯定感を育てましょう」と聞くと、確かに大事そうに思えますよね。
でも私はふと考えるのです。自己肯定感が高い=本当に幸せにつながるのか?
ただ「自信がある」だけで、中身が伴っていなければどうなんだろう、と。
自己肯定感=自分に価値があると思えること
心理学では、自己肯定感とは「自分には価値がある」と思える気持ちのこと。
欠点や失敗があっても「それでも自分は自分でいい」と受け止められる心の土台を指します。
よく似た言葉に「自己効力感(self-efficacy)」があります。
これは心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、「自分はこの課題を達成できる」という能力への自信を意味します。
- 自己肯定感 … 存在そのものへの安心感
- 自己効力感 … 行動や能力への自信
専門家が語る「自己肯定感」
発達心理学者エリク・エリクソンは、幼少期から「基本的信頼感」が育つことが、その後の人格形成に大きな影響を与えると指摘しています。
親に受け入れられ、泣いても安心できる経験が、自己肯定感の土台になるのです。
また、日本の教育心理学の研究でも「子どもが失敗をしても責められず、受け止めてもらえる経験」が自己肯定感の向上に直結することが示されています。
わが家の子育ての願い
私たち夫婦は、マルちゃんに「とにかく優しい子」に育ってほしいと思っています。
ここで言う優しさは、ただ「ニコニコしていること」ではありません。
- 人に思いやりを持てる
- でもズルい人、悪い人に振り回されず、きちんと線を引ける
- 負けない強さを持つ
マルパパの人生観
人生は、運と要領とタイミングだ
努力だけでは報われない場面もあるし、世の中には理不尽もある。
だからこそ、自分を信じつつも「運やタイミングに乗れる柔軟さ」も必要なのかもしれません。
泣かないマルちゃんとの会話
最近のエピソードです。
マルちゃんは転んでも泣きません。
「泣かなかったから偉いでしょ!」と誇らしげに言ってきます。
そのとき私はこう返しました。
「泣いていいんだよ。痛いときは“痛い”って言って泣いていいの」
我慢できるのは立派なこと。でも、泣く=弱いことではありません。
「泣いてもいい」「助けを求めてもいい」という安心感も伝えたいのです。
📚 そんなときにおすすめの絵本
「泣いてもいい」という安心感を伝えるなら、この絵本がぴったりです。
自己肯定感とどう向き合う?
心理学者カール・ロジャーズは、人が成長するために「無条件の肯定的配慮」が欠かせないと説きました。
つまり、結果や出来不出来に関係なく「あなたはそのままで大切だ」と伝えることが、自己肯定感を育むカギになるのです。
まとめ
「自己肯定感って何?」と改めて考えてみると、答えは一つではないように思います。
- 自分の存在を受け入れる力(自己肯定感)
- 自分の行動を信じる力(自己効力感)
- そして優しさや強さと結びつけていくこと
親としての声かけや体験の積み重ねが、子どもの「自分は大丈夫」という気持ちを育んでいくのだと思います。
自己肯定感を育てるおすすめ絵本&知育グッズ5選
最後に、子どもの自己肯定感を育てるのにおすすめのアイテムをまとめました。
1. 絵本「だいじょうぶ だいじょうぶ」
…
2. くもん出版「日本地図パズル」
…
3. 子育て本「自己肯定感の育て方」
…
4. レゴデュプロ「できた!」シリーズ
…
5. アンパンマン「よくできましたシールブック」
…

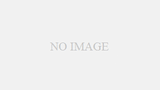
コメント